糖尿病
糖尿病とは
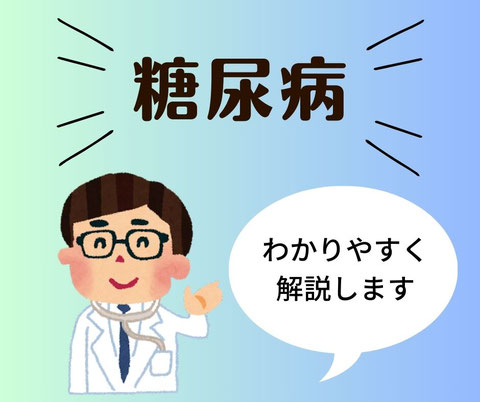
糖尿病は、血液中の糖を細胞に取り込む働きをするホルモンであるインスリンの分泌が低下したり、インスリンは分泌されているものの有効に働かないため血液中の糖をうまく利用できないことで様々な病気を引き起こす病気です。糖尿病の大多数を占める2型糖尿病では、遺伝的な要因などもありインスリンの分泌が低下したり、肥満が原因でインスリンを体中の細胞が有効に利用できないインスリン抵抗性のために血糖値が上昇します。過食や運動不足、ストレスなどの生活習慣が肥満の原因となることも多く、2型糖尿病では生活習慣病の側面が大きいです。血糖高値が長期間持続すると、全身の血管にダメージを生じるために、網膜症、腎症や神経障害などの合併症を起こしたり、また脳梗塞や心筋梗塞など心血管系の病気を発症するリスクも上昇するので、継続した治療が必要になります。そのために、2型糖尿病ではストレスを避け、適度な食事や運動を心がけることでインスリン抵抗性を解消するとともに、内服薬での治療や、病状が進行すればインスリンの注射で治療を行うことで、持続的に血糖をコントロールし、糖尿病により発症する合併症を予防することが非常に大切になります。
血糖とインスリンについて
体にとって大切な栄養素である糖は、血液の流れに乗って体中のあらゆる臓器をめぐり、体の種々の細胞が活動するためのエネルギー源となります。そして糖と同様に血液中に流れているインスリンの働きにより、糖は細胞内に取り込まれます。インスリンは膵臓で作られているホルモンで、糖尿病になるとインスリンがうまく働かず、血液中の糖をうまく細胞内に取り込めなくなるために、血液中に糖の成分が増加し高血糖になります。これには①インスリン分泌低下と、②インスリン抵抗性の二つの要因があります。膵臓で十分なインスリンを生成できなくなると、インスリン不足により血液中の糖が細胞に取り込めず、血液中に糖があふれてしまいます。またインスリンが作られていても、運動不足や過食などで肥満の状態が持続すると、インスリンが十分効果を発揮できない状態となり、これがインスリン抵抗性です。糖尿病には、絶対的なインスリン分泌低下を引き起こす1型糖尿病や、インスリン抵抗性が大きくかかわる2型糖尿病などがありますが、それぞれの発生機序により糖を有効に利用できなくなり血液中の血糖値が上昇してしまうため、さまざまな問題が引き起こされることになります。
糖尿病の種類と原因
糖尿病には大きく分けて1型と2型の2種類があります。1型糖尿病は、膵臓のインスリンを分泌するβ細胞が破壊されることにより、インスリン不足になることで起こる糖尿病です。その原因は現在の医学でも完全には解明はされていないませんが、体内の免疫の働きが正しく働かないといった自己免疫の働きが関わることでβ細胞が破壊され、絶対的なインスリン不足が起こることにより生じます。1型糖尿病は若い方を中心に幅広い年齢層で発症し、生活習慣が大きく関係している2型糖尿病とは原因や治療が全く異なり、全糖尿病の5%以下と言われています。一方で、糖尿病の大多数を占めるのが2型糖尿病です。2型糖尿病ではインスリンの分泌量が遺伝的に少なかったり、過食や運動不足などの生活習慣や、その結果引き起こされる肥満がインスリン抵抗性を助長することで相対的なインスリン不足となり起こります。太った中年以降の人に発症することが多く、生活習慣病としての側面が発症に大きく関与しています。それ以外の糖尿病としては、肝臓や膵臓の病気や、またクッシング症候群などの内分泌疾患などに伴い発症したり、他の病気の治療で使用するステロイドの薬の影響で糖尿病を発症する2次性糖尿病や、妊娠中に糖代謝が変化して起こる妊娠糖尿病などもあります。
糖尿病の症状と治療意義
糖尿病では当初は無症状のことがほとんどですが、病状がかなり悪化すると高血糖のために、喉が渇き、飲水量が増加して、尿の回数が増え、全身倦怠感や体重減少を認めることもあります。ただし、このような症状がはっきりと現れず無症状のこともしばしばあるために、糖尿病の存在に気がつかずに放置してしまう人もしばしば見られます。高血糖の状態を気がつかずに放置していると、糖尿病による合併症の症状が出現することがあります。高血糖の状態が持続すると、体中の血管がダメージを受け、様々な合併症を生じます。眼の微小血管がダメージを受け糖尿病性網膜症を発症すると視力が低下したり、毛細血管の障害により糖尿病性神経症をきたすと足や手の先のしびれを自覚することもあります。また、腎臓の血管がダメージを受けることで起こる糖尿病性腎症では、腎機能障害が高度になると腎不全となり透析治療が必要になることもあります。さらに心臓や脳に血液を送っている血管が閉塞すると、脳梗塞や心筋梗塞などの血管系の病気を引き起こし命に関わるることもあります。そのために、これらの病気が発生しないように治療を行ない、血糖を持続的に安定させることが糖尿病では必要になります。
糖尿病の検査と診断
糖尿病では、病状が進行すると倦怠感や体重減少、口喝、多尿などの症状を自覚することもあるものの、無症状のことも多いために、健診などを利用して、定期的に血液検査などの検査を行うことが糖尿病の早期診断には必要です。血液中の血糖値は食後どれくらい時間がたっているか、直前の食事をどれくらいの量食べたかなどにより、一日の中でも変化しています。そこで診断基準では、早朝の空腹時血糖が126mg/dl以上か、随時血糖(食後血糖)が200mg/dl以上のいずれかで血糖の上昇が確認され、かつ、ここ1~2か月の血糖を反映する採血項目であるHBA1c(NGSP)6.5%以上の両者が確認されることで糖尿病と診断されます。ただし実際の臨床の現場では、血糖値は食事量などにより変動も大きいため、HBA1cの値を見て診断や治療効果判定を行うことも多いです。また、肥満などの生活習慣の要因を認めない糖尿病や、若年発症の糖尿病や、高度の血糖上昇をきたす糖尿病の場合には、1型糖尿病の患者さんで上昇が見られる自己抗体の測定を血液検査で行うこともあります。さらに糖尿病の合併症の確認のため、血液検査での腎機能のチェックや、心エコーなどで心血管病変の可能性や、眼科での網膜症の有無などを検査して病状を評価することが必要になることもあります。
糖尿病の治療
糖尿病の治療は、1型糖尿病と2型糖尿病では異なります。1型糖尿病では、膵臓からのインスリンの絶対的な分泌低下が原因であり、インスリン製剤の注射が必須で、しばしば糖尿病専門医による治療が必要になります。一方、2型糖尿病では遺伝的な要素でインスリンの分泌量低下を認めていることもあるものの、ストレスや過食、運動不足などが引き起こす肥満状態がインスリン抵抗性を助長し、インスリンの有効利用ができなくなっていることが原因のことも多く、生活習慣病としての側面が大きいのが実状です。そのため、ストレスや過食を避けてバランスの取れた食事を心がけることが必要です。有酸素運動を行なうことで、糖を利用し細胞内に糖を取り込みやすくし、脂肪を減らし、インスリンが働きやすい環境を作るために、食事・運動療法を行うことが重要になります。糖尿病の内服薬にはインスリンそのものを摂取できる内服薬は存在しませんが、膵臓のインスリン分泌を促す薬、インスリン抵抗性を改善する薬、腸管からの糖吸収を減らす薬や、腎臓から尿中に糖を排出する薬など種々の内服薬があり、病状に応じてこれらの内服薬を組み合わせて治療します。ただし内服薬でコントロールが困難な時には、2型糖尿病でもインスリン注射での治療が必要になることもあります。

























